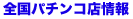【合同インタビュー】日本電動式遊技機工業協同組合 小林友也理事長 / 2年後に設置シェア10%を目指す「BT10」宣言 組合員一丸で掲げた目標に邁進
遊技日本2025年7月28日
今年6月13日に開かれた第45回通常総会で、理事長に再選した小林友也氏。ホール店舗数と参加人口の減少など依然として厳しい遊技環境で、新たなカテゴリであるBT機の普及など課題が山積している業界。どのように牽引していくのか、その胸中を聞いた(6月24日、日電協会議室にて)。
――今年6月2日、ついにBT機が導入開始となりました。心境はいかがでしょうか?
昨年8月に技術上の規格解釈基準の改正が行われ、同年9月より型式試験申請を開始してから、ようやく今年6月にBT機第1弾となる5機種を無事にリリースすることができました。今後も第2弾、第3弾と、継続的にリリースしていけるように考えています。
――理事長2期目のスタートを切りました。抱負をお願いします。
私の2期目の抱負は、第3のパチスロであるBT機の市場設置シェア10%を目指す「BT10」を宣言します。これはBT機が現状のパチスロでは満足できなかった離脱者や、新規ユーザーの受け皿となり、BT機の普及がパチスロユーザーの増加に繋がり、業界が活性化すると考えているためです。
第1弾の5機種を販売した組合員と意見交換を行った結果、BT10を目指すための課題が五つほど見えてきました。
――まず課題をお聞かせいただく前に、設置シェア10%はどのように決まったのでしょうか?
せっかくの新しい取り組みですから目標を作ろうとなりました。考えてみると私も30年ぐらい日電協にいますが、メーカーがまとまって一つの目標に突き進むということはおそらくなかったですし、面白いじゃない、やってみようと台数ではなく、およそ140万台のうちの10%(14万台)という数値目標を掲げました。
――ということは、ほとんどの組合員がBT機開発を進めているということでしょうか?
そうですね。現状、保通協や試験機関への持ち込みは半分近くがBT機です。これからみんなで市場を作っていくんだということを、真剣に考えている表れだと感じています。
AT機のほとんどはリールの20コマで作るわけですが、BT機の場合は21コマをうまく使いながらリーチ目を作ったりと、これは本来のパチスロの原点ですから作り手側はむしろ楽しんで開発しているという声も聞きます。
――ではBT10を目指すための課題についてお聞かせください。
一つ目は、「ホール様へのBT機の訴求不足」です。
何度も申し上げている通り、BT機は遊技性、射幸性を含めAT機とノーマルとの中間地点を目指しています。一方、先行したメーカーにホール様の意見を聞いたところ、ぱちんこの確変機をイメージしていたようで、射幸性の面で購入を控えたところもあったと聞いています。
業界の将来を見据えた場合、多種多様な遊技性、射幸性を持ったパチスロが必要であり、多様なユーザーのニーズに応えるために、BT機が必要なのです。もって、ユーザーの離脱を防ぎ、新規ユーザーの獲得にも繋がるものですし、このようなことをホール様に積極的に伝えていきたいです。
――二つ目は何でしょうか?
「ホール様のBT機のオペレーション」です。
先行5機種のデータを見ると、出玉率が低い傾向にあり、これは低い設定を使っているのではないかと類推されます。出玉の波が比較的緩いノーマルタイプは、ユーザーを引き留めるためにも、設定のオペレーションが大切です。BT機も出玉の波は比較的緩いので、ノーマルタイプと同じようにホール様での設定のオペレーションが重要となります。
――確かに、BT機を打ったユーザーの声で「設定が入っていないと勝てる要素がない」といったものが多く目につきます。
AT機の前の時代には、新規導入されたパチスロ機は、メーカーがホールに張り付き、ホール様の信頼関係の中で、設定のオペレーションを一緒にやってきました。BT機を成功させるためには、各メーカーがホール様との信頼関係をより一層築き上げることが重要なのです。
また、私もBT機導入店を回りましたが、ホールの中のどこにBT機が設置されているのかが分からず、サイネージ等には「新台導入」「BT機導入」などの案内はあるものの、店内を歩き回っても中々探せなかったのです。こうしたことを解消するため、今後BT機を販売するメーカーには、組合がBT機ポップを提供しようと思っています。
――課題の三つ目は?
「BT機のコーナー化の推進」です。
BT機という新しいカテゴリのパチスロですので、ホール様も様子見の中、小台数の設置となる傾向があります。BT機を生かすためには、ホールバラエティコーナーに埋もれさせてはならず、ましては、AT機に挟まれるように設置をされてはBT機が死んでしまいます。
これも各メーカーがホール様との信頼関係を一層築き、ホール様に提案をしていく必要があるでしょう。
――コーナー化をということであれば、機種数が圧倒的に足りてないと思いますがいかがでしょうか?
その通りで、課題の四つ目は「BT機の継続的なリリース」です。BT機は現状1機種で大量に販売できる機械とは考えていません。各メーカーが開発を止めてしまっては、BT10も達成ができません。これについては、BT機の継続開発を促すことを言い続け、またより良いBT 機が開発できるよう遊技性の向上を検討しなければならないと思っています。
五つ目は「BT機の遊技性の拡充」です。これについては今後行政と進めていきたい内容ですので、詳しくはまだ話せません。進展をお待ちいただければと思います。
――いずれノーマルタイプがBT機に入れ替わることもあり得そうですか?
その方がホール様のためにもなり得ます。一部は残ってもいいと思いますが、入れ替えた方がずっとホール様の経営も楽になるはずです。だからこそ逆に、面白いBT機を何としても作らなきゃいけないんです。
――減少する遊技人口についてはどうお考えでしょうか?
今の射幸性のバランスで見れば、入ってくるよりも止めていく人の方が多いでしょう。ですからまずは、止めていく人を少しでも減らす努力として、ノーマルタイプを増やし、射幸性のバランスを6(AT):4(ノーマル)くらいに変えていく必要性も感じています。そうした環境を整えながら、既存ユーザーが友達も誘ってみようかなと思えるような土台作りが今求められているのではないでしょうか。
昔のノーマルタイプはいろんなタイプがあって、それぞれみんな特徴があって面白かった。そういうものを我々メーカーが作らなければならないのです。
――メーカーだけでなく、ホール側も営業面で意識を変えていくことでしょうか。
メーカーも相当の努力をしなきゃいけないですし、ホール様も射幸性の低い台で経営するという経営努力が必要になります。そうした体質改善は1、2年で変わるものではなくて、10年、20年を経てみないと分からないですし、やらないと未来も変えれられません。BT機、これこそ新しいチャンスではないでしょうか。
――AT機のシェアが減って、その分BT機のシェアが増えることは射幸性の抑制にも繋がりますね。
そうした意味でも、BT機は行政も好意的に受け止めていると感じています。ただ、試験の在り方で通るものがなかなか通らないという問題もありますし、今後の課題でもあります。
――BT機でこれから期待できる点はありますか?
昔流行ったコンテンツ台をBT版として復刻させるのもありですし、何か一つヒット機を出したいですね。それは射幸性でヒットさせるのではなく、そうでないと業界は救えません。ホール様も販社も巻き込んでどうしたらファンが喜べるのか、そうした環境作りを一緒に模索していくのです。
私の務めはBT機を第3の柱、第3のパチスロ機として成⾧させることです。必ず、BT10を実現させて参ります。
――ありがとうございました。
日本電動式遊技機工業協同組合 小林友也理事長
1958年5月生まれ、東京都出身。東海大学工学部卒業。
日電協では1996年に監事に就任して以降、副理事長、筆頭副理事長を経て2023年に理事長へ就任。