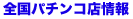日遊協、「パチンコプレイヤー調査2025」発表 コロナ禍後の遊びの変化と若年層の志向も調査
遊技通信2025年11月25日
一般社団法人日本遊技関連事業協会(日遊協、西村拓郎会長)は11月20日、「パチンコプレイヤー調査2025」の結果を発表する記者会見を行った。調査協力はエンタテインメントビジネス総合研究所の藤田宏氏が担当した。本調査はパチンコ参加人口の維持・拡大につなげる施策の基礎資料を目的に実施され、18歳以上を対象にインターネットリサーチで2025年8月1日から4日まで行われた。有効回答数は事前調査14,435サンプル(非遊技者含む)、本調査1,500サンプル(2〜3カ月に1回以上プレイする層)となっている。
調査では、コロナ禍以降のパチンコと公営競技の相関性に着目し、藤田氏は「単なるコロナ前後比較よりも、コロナ禍以降にどのような変化が起きたかを分析する方が有効」と指摘。外出制限によってパチンコ店に行けなかった期間に、オンラインで公営競技やネット系の遊びに流れたプレイヤーが一定数存在することが背景にあるという。
結果として、パチンコ遊技者のコロナ禍で遊ぶ頻度が増えた娯楽は「公営競技全体」が約33%で最も高く、「パチンコ」は約23%にとどまった。特に30代以下では公営競技利用が約45%増加しており、若年層の公営競技志向の強さが明確になった。最も遊びたい娯楽としては「パチンコ」が46%、「公営競技全体」が35%。高齢層ではパチンコ優先、若年層では公営競技優先の傾向がみられた。パチンコを選んだ理由は「一人で楽しめる」が43%で最多で、「好き」「暇つぶし」「気楽さ」が続いた。選ばなかった理由は「店舗に行く必要がある」が約20%で最多、次いで「他の娯楽より見返りが少ない」「イライラすることが多い」などが挙げられた。藤田氏は「店舗に行く必要があることはデメリットにもなるが、業界全体でメリットに変えていくことが課題」と述べた。
遊技スタイルでは、「実益を兼ねるがあくまで遊び」が最多で、遊技料金は4円が中心。世代別では、若年層は4円ハイタイプ、中年層は4円ミドルタイプ、高齢層は低貸しライトタイプを好む傾向があった。遊技頻度の増加理由は「使える時間が増えた」が約25%で最多。若年層は損しても楽しめれば満足、高齢層はトントンで遊べれば十分とする傾向がみられた。
遊技機については、スマパチは遊技経験者の認知率が約90%、打ったことがある人は約63%で昨年比でやや上昇。ラッキートリガー(LT)機は打ったことがある人が約68%で増加傾向にあり、LT突入時の達成感が人気だった。デカヘソ機は理解度・満足度が約59%で、特に若年層で高評価。羽根モノや役物機については、若年層は肯定的、高齢層は関心が低かった。未来の機能に期待する項目は、キャッシュレス決済が24%で最多、若年層はスマホ連動や協力プレイ機能、高齢層はオート機能やランキング機能に期待する傾向がみられた。スペックタイプ別満足度では、ハイタイプが最も高く、ライトタイプも高評価。射幸性はパチンコが約80%で最も高く認識され、若年層では「とても高い」と感じる割合が高かった。
新規参加者のきっかけは「友人・家族に誘われた」が44%で最多。若年層のPACHI-PACHIプロジェクト認知率は約9割、非遊技者では約7%に留まる。非遊技者のパチンコイメージは「ギャンブル」「タバコ臭い」が依然として強く、遊技者と非遊技者の間に大きな認識差がみられた。
20代以下の層は短時間・長時間で遊び方を使い分け、4円ハイタイプを好む傾向があり、勝利だけでなく「どれだけ楽しく遊べたか」を重視する。SNSなどでの情報感度も高く、多様なきっかけで遊技を開始していることがわかった。
藤田氏は今回の調査を踏まえ、射幸性に偏らない多様な遊び方の訴求、パチンコ店訪問のメリット強化、口コミやインフルエンサーを通じた新規層獲得を今後の課題と位置付け、「体験型施策や新規層へのアプローチを通じ、パチンコの楽しさを幅広く伝えることが重要」と述べた。