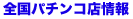ステマ規制は遊技業界に飛び火しないのか
遊技通信2023年2月1日
消費者庁の有識者検討会(正式名称は「ステルスマーケティングに関する検討会」)が昨年12月に、「口コミを装ったステマの法規制が必要」との報告書をまとめたそうです。
消費者庁 ステルスマーケティングに関する検討会
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_005/
日経ビジネス1月25日号によると、景品表示法を整備して2023年中に規制する見通しとのことで、SNSのインフルエンサーによる口コミが商品・サービスの売上げを大きく左右する時代に対応するものと言えます。有識者検討会が示した要件は、「広告主が投稿内容の決定に関与していないか」と「一般消費者が広告だと判別できるか」の2点です。
口コミが問題となるかならないかの線引きがポイントとなるわけですが、前者は、企業から商品サンプルを受け取った消費者が『自らの意思』で投稿した場合は問題となりません。それに対して後者は、依頼を受けた投稿者が『広告』や『宣伝』などと表示すれば、問題とはなりません。ただ、ステルスマーケティング(以下、ステマ)の依頼を受けたインフルエンサーのうち、約6割が「ステマに対する理解が低かった」と回答しています。
インフルエンサーのなかにはステマについての理解が十分ではないものの、ステマそのものを規制する法令がない以上、仕方ないのかもしれません。ちなみに、欧米ではステマを包括的に規制する動きがあり、消費者庁はそれに準じた対応を取ろうとしているのではないかと推察されます。ただしこれからは、インフルエンサーも知らないでは済まされない状況になっていくでしょう。
遊技業界では、警察庁が昨年12月に「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱い」が発出され、これまでとは異なる仕組みが動き出そうとしています。詳しくは他のプレミアム記事を読んでいただきたいところですが、広告宣伝にかかる文言や表現の規制が中心となっているようです。ぱちんこ事業者から依頼を受けたと見られる投稿がSNSでは多く見られるのも事実で、いわゆる「ステマ」が多く蔓延しているのではないでしょうか。風営法ではOKだとしても、他の法令(この場合は景品表示法)ではNGなのであれば、見直していく必要があるでしょう。
筆者紹介:伊藤實啓(いとう みつひろ)
株式会社遊技通信社代表取締役。1970年生、東京都出身。北海道大学大学院修了後、財団法人余暇開発センター(現、公益財団法人日本生産性本部)にて「レジャー白書」の編集およびギャンブル型レジャー産業の調査研究に携わる。祖父・伊藤重雄が創刊した、遊技業界で最も古い業界専門誌「遊技通信」を発行する株式会社遊技通信社に入社。編集部勤務を経て、父・伊藤登志夫の急死に伴い2002年から代表取締役に就任し、一般社団法人余暇環境整備推進協議会の監事としても活動中。業界団体や企業でのセミナー講師などを請け負う傍ら、企業経営にかかる専門的スキルをさらに磨くべく、法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科修士課程(MBA)を修了。中小企業診断士および認定経営革新等支援機関を取得し、地方自治体での窓口業務等を通じて、業界内外問わず企業経営者からの各種相談に応えている。2020年から法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科特任講師及び、2021年から国士舘大学経営学部非常勤講師も務める。